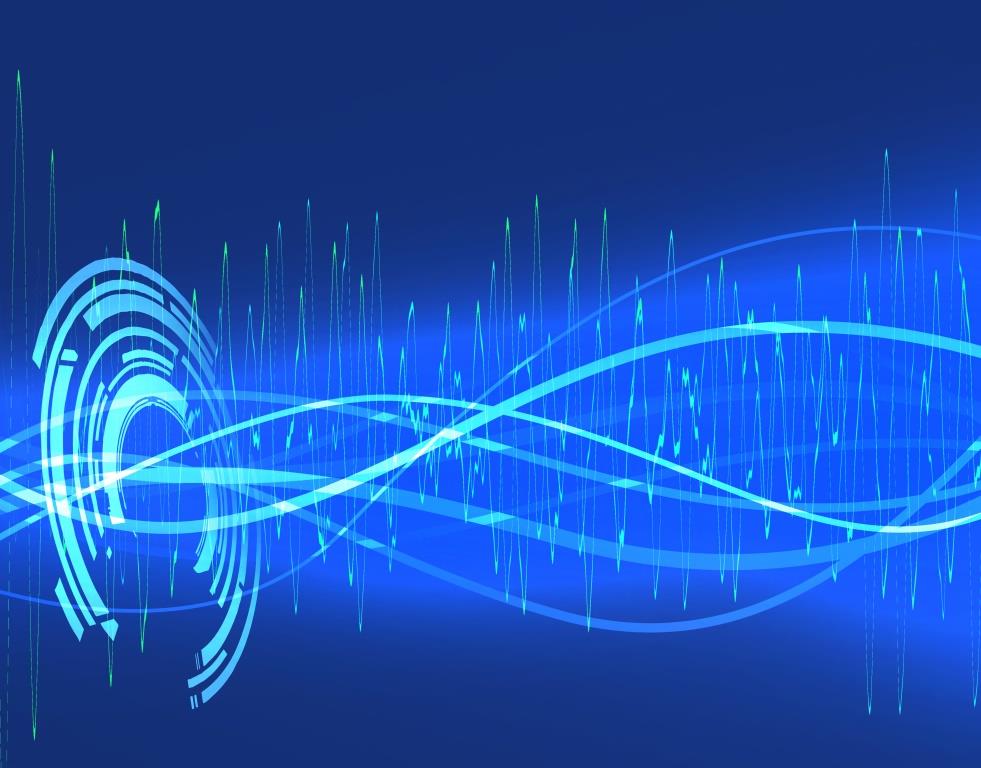


電波法認証(電波法)とは?
技適マークの必要性と認証制度について
電波法認証とは、無線設備が電波法の技術基準に適合していることを証明する認証です。「技術基準適合証明」「工事設計認証」の2種類があり、総務大臣の登録を受けた認定機関等が特定無線設備について、電波法に定める技術基準に適合していることを証明する認証および制度のことです。
つまり技術基準適合証明や工事設計認証とは、通信機器が電波法の基準に則ったものであることを証明するものです。 技術基準適合証明または工事設計認証を取得することで、その証として製品に技適マークを付けることが可能になります。
本記事では、主に電波法に基づいて適合を証明される「工事設計認証」について解説します。その概要や制度の詳細に加え、技適マークの必要性や、認証未取得による電波法違反のリスクまで詳しく見ていきます。
なお、
加賀FEIの全てのアンテナ付きモジュールは、日本の工事設計認証と、アメリカ・カナダの電波法認証を取得済みです。当社の無線モジュールをご購入いただいたお客様限定で、その他海外での電波法認証取得のサポートも行っています。
電波法と認証の取得について
電波法が定める技術基準に適合していることを証明する「技術基準適合証明」「工事設計認証」ですが、IoTデバイスなどの無線機を開発・販売するには、法令遵守という観点から電波法認証の取得が必須です。ただし既に電波法認証を取得済みの無線モジュールをデバイスに組み込む場合は、電波法認証を取得した条件下であれば、電波法認証取得が不要になります。
加賀FEIの無線モジュールは、日本・アメリカ・カナダの電波法認証を取得済みのため、これらの国で使用する場合は、モジュールを組み込んだ製品で新たに電波法認証を取得する必要はありません。
そのため、電波法認証取得に要する時間とコストを大幅に削減でき、製品を迅速に市場へ投入することが可能となります。
それでは、認証の基準となる、電波法そのものについて確認していきましょう。
電波法とは、限られた電波を公平かつ効率的に利用するための法律で、違法な電波や強力すぎる電波が周囲の機器に混信を起こしたり、他の重要な通信を妨害したりすることを防ぐ意図があります。
電波法上では、通信のために電波を発する機器はすべて無線局という扱いになり、通信機器を使用する(無線局を開設する)ためには、原則免許制となっています。ただし、小規模な無線局においては下記のように、例外的に免許なしでの取り扱いが認められています。
“ 携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、使用者の利便性の観点から、事前に電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、免許手続時の検査の省略等の無線局開設のための手続について特例措置が受けられます。 ” (出典 : 『総務省電波利用ポータル』 https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/index.htm)
小規模無線局を取り扱うユーザーがこのような特例措置が受けるために、電波法に基づく認定機関の検査と証明を受け、免許なしでも技術基準に適合していることを証明するものが「技術基準適合証明」および「工事設計認証」になります。
電波法認証を取得していることを、
“
技適取得済み” などと言われる場合もあります。この場合の技適とは、「技術基準適合証明」または「工事設計認証」のいずれかを指していることになります。

技術基準適合証明と工事設計認証の違い
どちらも電波法に基づく無線設備の技術基準適合性を証明する制度ですが、対象や審査内容、認証番号の付与などに違いがあります。
| 技術基準適合証明 | 工事設計認証 | |
| 試験対象 | 完成した全ての無線機器・設備 | 無線機器・設備の設計 |
| 審査内容 | 無線機器・設備 1台ずつ全てが
技術基準に適合しているか |
設計・製造段階での品質管理などが
技術基準に適合しているか |
|
番号の付与
|
1台ごとに証明番号を付与 | 設計(型式名など)ごとに
認証番号を付与 |
|
証明の表示
|
技適マーク | 技適マーク |
|
主な対象製品
|
試作品・少量生産品 | 大量生産品 |
「技術基準適合証明」は、すべての機器に対して1台ごとに試験が行われます。審査台数が多いため手数料が高額となりやすい傾向にあります。証明対象の数にも限度があるため、試作品や少量生産向けの制度です。
一方、「工事設計認証」は、対象機種や型名ごとに審査を行います。無線機そのものではなく工事設計を対象としているので、無線機の完成品は認証後に製造される点が技術基準適合証明と異なります。無線機の台数には制限がないため大量生産向けの制度ですが、製品の品質や、製造される全ての無線設備を基準に適合させるための試験方法などを詳しく説明するために必要な書類が多く、審査が厳しいことから、技術基準適合証明よりも認証の取得が難しくなっています。
なお、加賀FEIのアンテナ付きモジュールは、量産製品として「工事設計認証」を取得しています。
技適マークの見方と有効性
技適マークについて
技適マークは、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークで、「技術基準適合証明」または「工事設計認証」いずれかの認証が取得できていることを表示するマークです。
技術基準適合証明番号や工事設計認証番号を確認することで、いつ、どのように認証された機器かを調べることもできます。
技適マークと工事設計認証番号は、主に機器の背面や底面、あるいはバッテリーカバーの裏側などに刻印やシールとして貼付されていることが一般的です。スマートフォンなどの場合は、ソフトウェアから設定画面を開くことで工事設計認証番号が確認できるケースも存在します。また、機器が小さ過ぎて技適マークや工事設計認証番号を記載できない場合は、パッケージと取扱説明書に記載することになっています。
スマートフォンやパソコン周辺機器など、多数の電子機器に工事設計認証番号が付与されていますが、海外製品の中には表示が見当たらないものも存在します。そのような機器は、輸入段階で日本の電波法認証を取得していない可能性があり、日本国内での使用が違法になるケースもあるため注意が必要です。
電波法認証の有効性
国内で無線機を使用するために必須の電波法認証ですが、工事設計認証を取得済みの無線モジュールを組み込むことで、最終製品での電波法認証取得は省略することができます。認証を取得していないモジュールを最終製品に組み込んで使用する場合は、最終製品で電波法認証の取得が必要になります。
ただし工事設計認証取得済モジュールを使う際も、認証を取得した時と違う条件で使用する場合は、改めて電波法認証を取得しなくてはなりません。
また、国ごとに電波法認証制度は異なります。ある国で電波法認証を取得していれば有効な国もあります。無線機をどの国・地域で使用するかを確認した上で、それぞれの国に合致した電波法認証を取得する必要があります。
電波法認証の必要性と法律的側面
では、使用する機器に技適マークがないとどうなるのでしょうか?
電波法認証違反のペナルティとトラブル
一部の無線機を除いて、機器本体またはパッケージと取扱説明書に技適マークが付いていない無線機を使用すると、電波法違反になる恐れがあります。電波法に違反した機器を使用すると、個人であっても罰金などの厳しい処罰が科される可能性があります。これは国家が電波を公共財として管理しているためであり、無秩序に電波を発信すると他の重要通信を妨害するリスクがあるからです。
なお電波法認証を取得した機器は免許不要で使用できますが、規定外の改造や破損などで基準を満たせなくなると、電波法認証が無効になる場合もあるため注意が必要です。
このように技適マークのない機器や、電波法認証取得後に改造して基準を満たさなくなった機器を使用する行為は電波法違反として扱われ、行政処分や刑事罰が適用される場合があります。個人でも、最大100万円以下の罰金や懲役刑が科される可能性があり、法律的側面からも電波法認証を意識した機器選びが重要になります。
また、電波法認証を取得していない機器を使ってしまうと、法律外のデメリットも多く、違法性のある状態で利用し続けることのリスクは高いため、技適マークの有無についての確認は欠かせません。
安全面から見る重要性
電波法認証の取得は安全面でも大きな意味を持ちます。例えば、航空無線や医療機器の通信を妨害するような強い電波が出れば、重大な事故につながる恐れもあります。電波法認証制度が存在することで、そうした不測の事態を防ぎ、利用者が安心して通信技術を活用できる環境を確保しているのです。
海外製品の電波法認証問題
海外から輸入されたスマートフォンや無線機器の中には、現地の基準はクリアしていても日本の電波法認証を取得していないものがあります。こうした機器を日本国内で使用すると電波法違反に該当する場合があり、購入や使用には大きな注意が必要です。海外製品を使う際には、日本向けの技適マークが付いているかを事前に確認することが重要になります。

まとめ
電波法認証制度は、日本の電波環境を健全に保ち、ユーザーが安心して通信機器を利用できるように設けられた制度です。IoTデバイスをはじめ、無線通信を行う製品にとっては必須の要件であり、無視すると法律違反や深刻なトラブルに発展しかねません。特に海外製品を利用する場面では、技適マークの確認が欠かせません。
正規の手続きを経て電波法認証を取得すれば、製品の信頼性だけでなく、法律面や安全面でも多くのメリットが得られます。企業にとっては市場投入のハードルが高く感じられるかもしれませんが、利用者にとっては安心できる根拠であり、円滑な通信環境を維持するためにも欠かせないプロセスといえるでしょう。
電波法認証や無線モジュールについてのお困りごと、気になる点などございましたら、お気軽にご相談ください。

